 こひつじさん
こひつじさん特養での仕事ってどんな感じなのかな?
特養の求人、最近よく見かけませんか?
ここ数年で、特養でもリハビリを提供する流れが来ており、求人を出す事業所も一気に増えています。
でも「やったことないし…」と敬遠している療法士さん、実はかなりもったいないです。
特養は、40代・50代の療法士にとって「経験を活かして長く働ける」職場のひとつ。
 おだかすみ
おだかすみこう言い切れるのは、私自身、特養2ヶ所で働いた経験があるから!
この記事を読めば、
- 特養で働くメリット
- 特養での仕事内容
- 向いている人の特徴
- 特養への転職を成功させるポイント
が、全てわかります。
読み終わる頃には、特養で働くという選択肢を前向きに考えることができるはず。
特養のお仕事に興味のある方は、ぜひ続きをお読みください。
40代療法士に特養がおすすめな理由

特養は40代療法士にこそ向いている職場です。
ここではその理由を3つに分けて解説します。
体力的に無理なく続けられる
特養は、病院や老健のように「単位ノルマ」に追われることがありません。
訓練頻度や内容を自分で調整できるため、体力的な負担をコントロールしやすいのが特徴です。
例えば…
- 生活リハビリは介護職と分担し、療法士は関節可動域訓練や姿勢調整に集中
- 無理に立位練習を繰り返さず、機能維持を目的に安全な方法を選ぶ
- 集団体操を取り入れ、効率よく複数名にアプローチ
40代になると「以前のようにバリバリ動けない」と感じることも増えますが、特養なら無理なく調整しながら働けます。
この「柔軟に負荷を調整できる環境」が、長期的に働き続けられる大きな理由です。
他職種と連携しやすく、立ち位置が明確
特養は一人職場になることが多く、介護士・看護師・栄養士・相談員など他職種との連携が欠かせません。
このとき、40代療法士の「年齢による落ち着き」と「現場経験による説得力」は大きな武器になります。
若手のうちは、どうしても他職種に対して気後れしてしまうことがあります。
しかし40代ともなれば、「何を優先すべきか」「どんな説明をすれば納得してもらえるか」が自然と身についています。
わたしの体験談
実際、私も35歳を超えて特養へ異動した際、年齢と経験のおかげで他職種との話し合いがスムーズに進みやすかったです。
冷や汗をかきつつも「やるべきこと」を明確に伝え、お局看護師さんにも堂々と協力を依頼できたのは、年齢によるアドバンテージが大きかったと思います。
結果、療法士としての立ち位置を確立でき、介護職のサポート役としてではなく「専門職」として信頼を得ることができるようになります。
幅広い知識を活かしやすい
特養は、一人でご利用者さんの状態を見極め、必要なアプローチを決めなければなりません。
このとき役立つのが、40代までの経験で培った「幅広い知識」です。
PTさんはこういう人に歩行器を勧めていたな
STさんはこういう食べ方は危ないから食形態を下げた方がいいと言っていたな
この知識が、特養で仕事をしていく上で非常に重要となってきます。
若手のように「何をすればいいかわからない」と立ち止まることが少なく、現場に入ってすぐに即戦力として活躍できるのも40代療法士が特養で働く魅力です。
この3つの理由から、特養はまさに40代療法士のキャリアにぴったりの職場と言えます。
次は、特養の基本的な特徴や仕事内容を確認していきましょう。
特養ってどんな場所?
特別養護老人ホーム(特養)は、要介護度が高い高齢者が「最期まで安心して暮らせる場所」を提供する施設です。
家族の介護負担を軽減し、医療や在宅サービスだけでは支えきれない部分を補う、いわば“地域の最後のセーフティネット”の役割も担っています。

特養利用者の特徴
ご利用者さんの特徴は以下のとおり。
- 原則、要介護度3以上
- ※重度認知症や家庭の事情で要介護1・2でも入所可能
- 85歳以上の高齢者が中心
- 常時介護が必要で、在宅生活は困難
- 「終の住処」として入所し、看取りまで対応する方も多い
このような方々が対象のため、特養のリハビリは「改善」よりも「生活を支える」視点が基本です。
療法士の配置と役割
特養に療法士の配置義務はありません。
ただし介護保険上「機能訓練指導員」を1名以上配置することが義務付けられています。
- 配置基準:入所者100名に対して機能訓練指導員1名以上
- 対応資格:PT・OT・ST・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師など
- 実態:1名のみの配置が多く、療法士であっても「一人職場」になるケースがほとんど
 こひつじさん
こひつじさん高齢者100人に対して療法士1人!?
最初は驚きますが、業務は病院や老健に比べるとシンプルです。
 おだかすみ
おだかすみ今度は、機能訓練指導員として療法士が何をしていくのかを見ていくよ〜
機能訓練指導員の業務内容
機能訓練指導員の仕事に関係する加算は以下のとおり。
- 個別機能訓練加算
専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、個別機能訓練計画を作成・実施した場合に算定できます。 - 経口維持加算
摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、多職種が協働して経口維持計画を作成し、経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行った場合に算定できます。
この中で必ずといって求められるのが、個別機能訓練加算です。個別機能訓練加算を算定するためには下記の業務を行う必要があります。
生活機能チェックシートの作成

- 厚生労働省の様式を用いて、ADL・IADL・基本動作を確認
- 例:「立位保持:5秒可能」「車椅子操作:見守りで可能」など、シンプルな記載が中心
- 他資格者でも書けるよう設計されているため、詳細な専門評価までは不要
実際の現場では、1人あたり数分〜10分程度で記入できることがほとんどです。
個別機能訓練計画書の作成

こちらが特養で記入する、個別リハビリテーション実施計画書です。
病院や老健で使用されている計画書に比べて、だいぶシンプルな内容となっています。
- 内容は「歩行練習」「食事動作」「座位保持」など日常生活に直結するものが中心
- 集団訓練や介護職員による生活リハビリもプランに組み込める
- 訓練時間の制約なし
- 最近は「個別機能訓練・栄養・口腔」の一体型計画書を採用する施設も増加(書く内容はほぼ一緒)
例えば、「週2回10分、立位保持練習」など、現実的に実施できるプランを立てるのがコツです。
ご本人またはご家族への説明
計画の内容をご本人やご家族に説明し、同意を得ます。
専門用語を避けてわかりやすく伝えるのがポイントです
計画内容の実行、記録、3ヶ月ごとの見直し
- 実施した訓練内容を記録
- 3カ月ごとに再評価・計画見直しを実施
最近は電子記録システムを使用している事業所が多く、その中に訓練記録を書く欄もちゃんと用意されています。
電子記録がない場合は自分で経過記録を作成します。様式に決まりはありませんが、いつ、誰が、どのような内容を行なったか、その時の様子を記録する必要があります。
現場でよくあるスケジュール例
- 午前:集団体操+フロアでの見守り+個別訓練
- 昼食時 : 昼食介助、評価
- 午後:個別訓練、作業活動(たたみもの等)、記録
- 合間に介護職と情報共有やカンファレンス
「リハビリ室でひたすら個別リハを回す」スタイルではなく、生活の場に入り込みながら「できることを支える」イメージに近いです。
100人対1人でもやっていける理由
- 評価・計画はシンプルで、専門的すぎる内容は求められない
- 他職種と連携して「生活リハ」を進められる
- 仕事のペース配分を自分で調整できる
 こひつじさん
こひつじさん確かに書式はシンプルだけど…。一人で入所者全員分の評価をして計画書書書いてリハビリもするなんてムリだよ〜
 おだかすみ
おだかすみ一人でぜんぶ、と思うとびっくりするよね。
次は100人対1人でも穏やかにお仕事するための心構えを教えるよ。
特養で働くための心構え 3選

特養は、100名規模の入所者に対して機能訓練指導員は1名だけ…というケースがほとんど。
病院や老健のようにリハビリスタッフ同士で相談できる環境ではないため、これまでの常識が通用しない場面に直面することもあります。
ここでは、特養で働く前に知っておきたい3つの心構えをご紹介します。
ぜんぶ完璧にやろうとしない
「100人全員をしっかり評価して、計画書も丁寧に作って…」
最初はそう考えがちですが、それでは一日が終わってしまいます。
【体験談】
私も特養に異動したばかりの頃、全員にMMTや認知機能検査を実施しようとしていました。
ですが、評価に追われて入所者さんと話す時間もなく、他職種との連携も不十分…。
しかも、その詳細な評価結果が実際のケアに活かされる場面はほとんどありませんでした。
結局「自己満足のための評価だった」と気づき、それからは割り切るようにしました。
ポイント
- 評価は「最低限」でOK
- 訓練は「できる範囲」でOK
- あとは介護職や看護師に「生活リハビリ」をお願いする
生活リハビリの例
- 体位交換時の寝返り練習
- 移乗時の端座位保持練習
- トイレ動作時の立位保持練習
- 食事時の自力摂取練習
特養では、療法士が直接介入する回数は週1〜2回程度が限界です。
だからこそ「チームで支える」視点が欠かせません。
 おだかすみ
おだかすみ「人に頼る」ようになってから、気持ちも体も楽になったよ
何より優先されるのは「安心」と「安全」
 こひつじさん
こひつじさんこれまで当たり前にしてきた評価や訓練をしなくていいって言われてもなぁ〜。
特養で働くことになったら、ゴールの位置を少し変える必要があります。
機能を回復する → 機能を維持する
できることを増やす → 今できていることをできるだけ長く続ける
特養は「体を治す場所」ではなく、「生活の場所」です。
そして生活の場所で求められるのは厳しいリハビリではなく、「安心」して「安全」に生活できる環境です。
ここで暮らす方々に、いかに苦しい思いをせずに人生最後の時間を過ごしていただくか。
これが特養で働く機能訓練職員の最大のミッションとなります。
療法士の職種は関係ない
ここで、衝撃的な事実をお伝えします。
特養で求められる療法士の役割に、職種の違いは関係ありません。
PTでもOTでもSTでも、実は同じ役割を求められます。
 こひつじさん
こひつじさんえ、ぼくPTの仕事しかできないんだけど
 おだかすみ
おだかすみ私はSTだけど、特養でお仕事するとなったら「それしかできない」とは言ってられなかったよ
ここは病院とは大きく違う点です。
- PTでも、嚥下の相談を受けることがある
- STでも、歩行器や車椅子の相談に乗ることがある
もちろん専門的に深掘りする必要はありませんが、基本的な知識と「調べながら対応する姿勢」が求められます。
まだ臨床経験の浅い新人にはハードルが高いかもしれません。
ですが40代の経験豊富な療法士なら「幅広く対応する力」を活かせる場面が多いはずです。
特養で多い困りごとと対処法
 こひつじさん
こひつじさんでもやっぱり不安だよー。トラブルとかないの?
特養は一人職場になりやすい環境です。
実際に働き始めてみると、孤独感や人間関係、業務量の多さなど、想像していなかった悩みに直面することもあります。
ここでは、特養でよくある7つの困りごとと、実際に私や周りの療法士が実践してきた解決策を紹介します。
「こんな時どうするの?」と気になる項目があったら、開いてみてくださいね。
一人で寂しい
困りごと: 他に療法士がいないため、孤独を感じやすい
対処法:
- 割り切って「計画書作成と実行」に集中
- 他職種とは必要以上に深く関わらず、適度な距離感を保つ
- 一人であることのメリット=「対人トラブルが少ない」と考える
ここは割り切りが大切です。
私たちはあくまで機能訓練指導員として仕事をするために雇われています。
周りとの距離感を持って仕事することで、過剰なストレスを感じずに働くことができるようになります。
あたりの強い介護・看護職員がいる
困りごと: 苦手な職員との関係にストレス
対処法:
- 苦手な相手との接点を最小限に調整
- 管理職など避けられない相手には以下を実践
- 小さな頼み事をして感謝を大げさに伝える
- 良いところを見つけて褒める
→「私は敵じゃないよ」という姿勢を示すだけで、仕事がやりやすくなります。
どこの職場にも、相性の合わない人の一人二人はいるものです。
仲良くはなれなくても仕事をする上で必要最低限の言葉のやり取りができたらそれでヨシ、という割り切りも必要です。
何をしていいか分からない
困りごと: 入職直後、業務の優先順位が分からない
対処法:
- 10分刻みのスケジュール表を作成
- 個別リハは「週1〜2回できればOK」と割り切る
- 「今日何しよう…」という不安を防ぐには計画表が有効
入職直後は特にこの状態になりやすいです。
まずは大まかなに時間割を作成し、それを徐々にアレンジしていくのがおすすめです。
やたらと介護職員さん向けの勉強会や研修を依頼される
困りごと: 頻繁に講師役を頼まれて負担
対処法:
- 毎年同じ資料を使い回せる仕組みを提案
- 研修部会の職員と共同で進めるよう依頼
- ディスカッション形式にして資料作成を最小限に
「この人はリハビリの職員なんだ」と認識されると、施設内研修の講師を依頼されることが頻繁にあります。
内容は移乗介助方法や福祉用具(スライディングボード等)の使い方、ポジショニング、食事介助方法についての指導が多いです。
この研修、1回2回であればまだいいですが、毎年・毎回と頼まれる頻度が多くなると準備だけでもかなりの時間が取られます。自分は人に教えるのが好きなんだという療法士さんはいいですが、ちょっと苦手、、という方には上記の対処法をおすすめします。
職員全員に実技指導するように言われて毎日残業する羽目になった、という話も聞きます。
際限なく仕事を任されて苦しくなることがないよう、自分の身は自分で守っていきましょうね。
生活リハビリをしてもらえない
困りごと: 他職種に協力してもらえない
対処法:
- 「毎回じゃなくてもいい」と選択肢を与える
- ご利用者の「意外な一面」を発見してもらう=「自分だけが知っている!」という喜びにつなげる
→ やらされ感を減らし、自発的に協力してもらえる空気をつくることが大切
これもあるあるです。
他職種にとっては忙しい日々の業務の中にさらにやることが増えるわけですから、嫌な顔をされるのはある意味当然と言えます。
誰でも「やらされる」のは嫌なもの。プライドを持って仕事している人にとっては尚さらです。
そのお気持ちを尊重し、今日は1回でも生活リハビリしてもらえたらいいな〜とゆったり構えることがストレスを減らすポイントです。
人の行動を変えるのは想像以上に時間がかかります。時間をかけて習慣を浸透させていくイメージが大切ですよ。
長期で休むことになった
困りごと: 一人職場のため、休みが不安
対処法:
- 最低限必要なのは「3ヶ月ごとの計画書作成」だけ
- 休んだ期間は記録に残しておけば問題なし
- 1ヶ月以上休む場合は、早めに施設へ連絡し代替指導員の登録を確認
感染症や家族の看病で長く休んでしまった…そんな事態は誰にでも起こりえます。
一人職場だと周りのフォローも受けられないし、もうだめだー、、と肩を落とす必要はありません。
機能訓練指導員として最低限やるべき仕事は、「3ヶ月に1回の個別機能訓練計画書の作成」です。
個別リハビリを週○回必ずやること、という決まりはなし。
仮に1週間2週間個別リハビリがお休みになったとしても、今のところそれを罰する規則は確認されていません。
ただし他職種が行なった生活リハビリの記録は残しておく必要はありますし、訓練再開時には”○月△日〜○月△日の期間、機能訓練指導員体調不良のため個別訓練実施せず”と記載するのがベター。
また1ヶ月以上休むとなると個別機能訓練加算の算定要件を満たさなくなるため、早めに職場に連絡し、代わりの機能訓練指導員の登録が可能か確認することをおすすめします。
給料が低い
困りごと: 特養の療法士は給与が低め
対処法:
- 「機能訓練指導員+α」の付加価値を作る
- 成果を「見える化」し、給与交渉の材料に
- 他に療法士がいない環境は、交渉のチャンスでもある
特養療法士の給与は残念ながら低いことが多いです。
その理由は明白で、特養には療法士が絡む加算が少なく、リハビリで大きな収入を得ることが難しいためです。
これに対する対策として考えられるのは、「自分に付加価値をつけて交渉する」ということ。
私の友人の話ですが、地域貢献活動として行なっていた地域の茶の間の体操教室でファンを増やし、営業に貢献するという付加価値を自分につけたそうです。
それだけでは誰も評価してくれないため、茶の間に来てくれる方にアンケートを取り、結果を年に1回の施設長との面談の際に直接見せるという方法でアピール。
その行動によって、「上席機能訓練指導員」という新しい役職をつけてもらったということです。
この方法は誰にでもできることではないですが、特養は他の療法士に遠慮することなく給与アップの交渉を行いやすい環境です。まずは機能訓練指導員+αの自分の価値を探してみましょう。
特養に向いている療法士の特徴

ここまでの内容で、特養で働く不安が少し減ってきた方もいるのではないでしょうか。
次は、実際に特養で働く療法士の声をもとに「特養に向いている療法士の特徴」を紹介します。
1. 給料より休みやすさを重視する人
仕事のやりくりを全て自分でできるので、休みやすい
こんな声を特養療法士からよく聞きます。
自分で業務の計画を立てて実行できるため、周りに遠慮せず休みを取りやすいのは大きなメリットです。
ただし給与は病院と比較して低めなので、それを許容できるか、自ら上げていく気概があることが条件になります。
「給与も大切だけど家族との時間も大切にしたい」
「生活のゆとりも大切にしたい」
という方には特養は向いていると言えるでしょう。
2. 体力面に不安がある人
あくせくしないで、ゆったり働ける
こんな声もよく聞かれます。
病院や老健のように忙しく動き回る職場とは違い、特養は比較的ゆったりした時間が流れています。
もちろん業務はありますが、ペースを自分で調整しやすいのが特徴です。
40代を過ぎて「以前より体力に自信がなくなってきた」と感じる方にとって、無理なく働ける職場環境といえるでしょう。
3. 計画を立てるのが好きな人
ぜんぶ自分次第だから、ワクワクする
こう思える人は、ぜひ特養に来てほしいです。
特養は利用者の入れ替わりが少なく、機能の劇的な改善もあまりありません。
「毎日が同じことの繰り返しで退屈…」と感じる人もいますが、一方で、楽しそうに働いている人もいます。
その違いは「自分で計画を立てて実行することが好きかどうか」。
他職種と連携しながらも、機能訓練指導員としての業務は基本的に一人で進めます。
自分でスケジュールを決めて、コツコツと遂行するのが得意な方には、特養はぴったりの職場です。
特養への転職を成功させるポイント

 こひつじさん
こひつじさんちょっと特養に興味か出てきたよ。
けど転職ってどうすればいいの?
特養転職に興味はあるものの、
「どの求人を選べばいいか分からない」
「職場の雰囲気が想像できない」
そんな悩みを抱える療法士さんは多いと思います。
 おだかすみ
おだかすみ特養は施設によって雰囲気が全然違うから、いかに深い情報を集められるかが鍵になるよ
ここでは、特養転職をスムーズに進めるために知っておきたいポイントを解説します。
求人の探し方
求人探しには主に「転職サイト」と「転職エージェント」の2つの方法があります。
| 求人の探し方 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 転職サイト | 自分で求人を検索・応募 | じっくり比較検討したい人 |
| 転職エージェント | 専任の担当者が求人紹介・調整 | 効率的に転職したい人、内部情報がほしい人 |
特養は「内部情報が分かりにくい」職場です。求人票だけでは、
- 療法士を雇用することになった背景
- 療法士に期待する仕事内容
- 残業や休日の取りやすさ
といったリアルな情報は見えてきません。
だからこそ、特養転職にはエージェント活用が有効です。
転職エージェントのメリット
特養転職でエージェントを利用することのメリットは以下の通りです。
- 内部情報が豊富
「介護職との関係性は?」「残業はある?」など、求人票では分からないリアルな情報を事前に確認できます。その情報こそが失敗回避の決め手になります。 - 強みを言語化し、給与交渉を代行
自分では言いにくい給与交渉も、エージェントがあなたの強みを整理して代わりに交渉してくれます。
転職エージェントは転職をさせるプロなので、強みの伝え方もバッチリ。強みを相手に的確に伝え、できるだけ高い給与を提案してもらうことも可能です。 - 求人募集が出ていない特養に直接アプローチしてもらえる
「この施設気になるけど求人が出ていない…」という場合でも、エージェントが施設に直接問い合わせてくれるサービスがあります。

PTOT人材バンクでは、求人を募集していない事業所に「こんな人いますよ、どうですか」と交渉してくれる独自のサービスがあります。
特養は、求人募集を出していなくても「良い人がいたら採用したい」と考えている施設が多いのが実情です。
PTOT人材バンクを利用するとこうした施設に自分からアプローチできるため、希望の地域で勤務できる可能性を高めることができます。
ちなみにこれらのサービスはすべて無料。
▼ 仕組みはこの記事で解説しています▼
\ 年間11.000人の利用実績あり /
▲ 60秒で簡単登録、ずっと無料 ▲
転職エージェントのデメリット
もちろん、転職エージェントにも注意点はあります。
- 登録後に電話でヒアリングを受ける必要がある
- 担当者との相性によってはストレスになることがある
- 転職を急かされていると感じる場合がある
登録後の連絡は、登録数分後に来る場合もあるため、かなり驚きます。
しかも返事をするまで連絡が来るため、「しつこい」と思われることも多いようです。
この連絡は、「今どんな状況で、どういった情報が欲しいと思っているのか」を直接確認するために行われるもの。
決して転職を急がせたり無理強いするためではないので、落ち着いて話をしてみて下さいね。
▼ 登録後の流れが不安な人はこちら ▼
それでも
「担当がつくなんて嫌だ」
「自分のペースで進めたい」
という場合には、転職サイトの利用についても検討をおすすめします。
まとめ|特養は40代療法士の新しい選択肢
特養は、体力的に無理なく働けて、これまで培ってきた幅広い知識や経験を存分に活かせる職場です。
確かに一人職場や独特の業務スタイルに戸惑うこともありますが、心構えや働き方を知れば、むしろ「長く安定して働ける環境」として大きな魅力があります。
この記事でお伝えしたポイント
- 特養は40代からのキャリアに最適
- 「完璧を目指さない」ことで、無理なく仕事を続けられる
- 生活リハビリや他職種連携を通して、チームで入所者を支えることができる
- 転職エージェントを活用すれば、非公開求人や職場の雰囲気まで把握できる
もし今、「病院は体力的にきつい」「もっと落ち着いて働ける環境に移りたい」と感じているなら、特養という選択肢を真剣に考えてみる価値があります。
自宅近くに特養の募集があるかどうか、まずは相談してみましょう!
\ 年間11.000人の利用実績あり /
▲ 60秒で簡単登録、ずっと無料 ▲
無理のない働き方と、あなたの経験を活かせる環境を見つけることができますように。
 おだかすみ
おだかすみあなたの挑戦を、心から応援しています!
それでは良き療法士ライフを!!
関連記事一覧
▼ クリックで開けます ▼
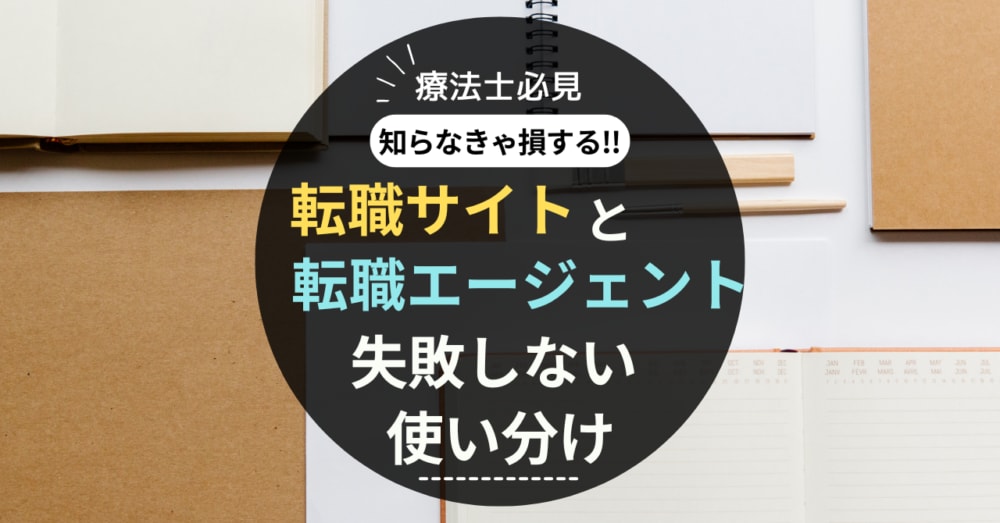
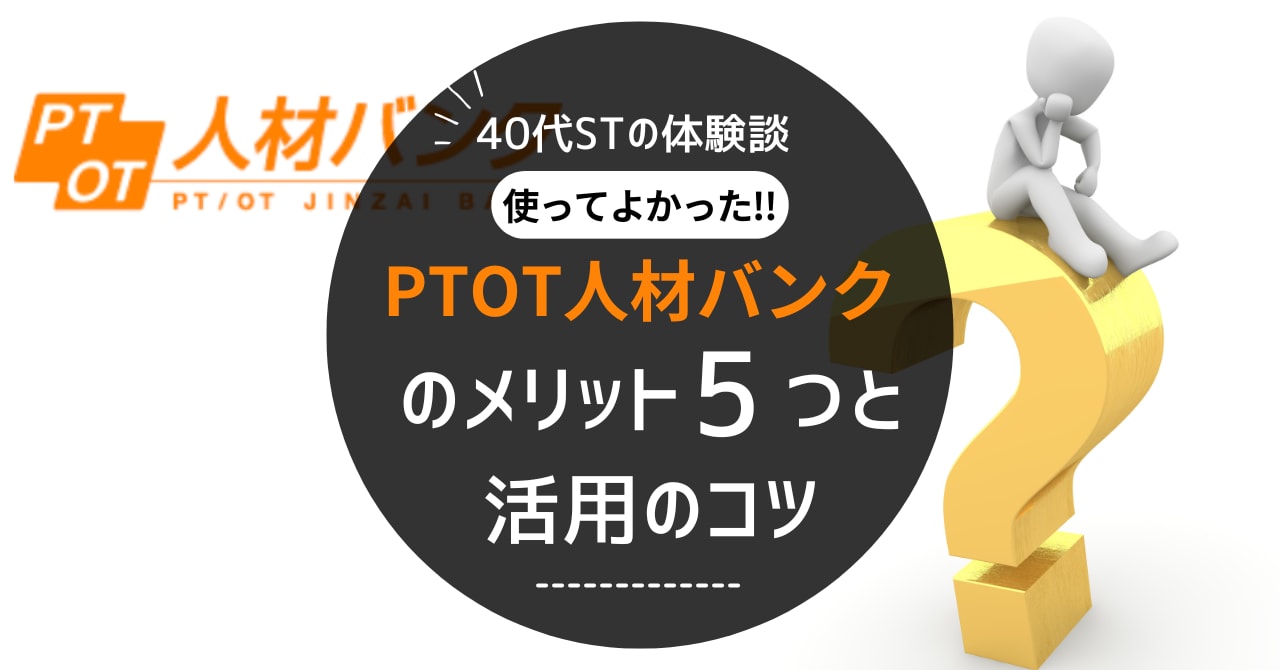
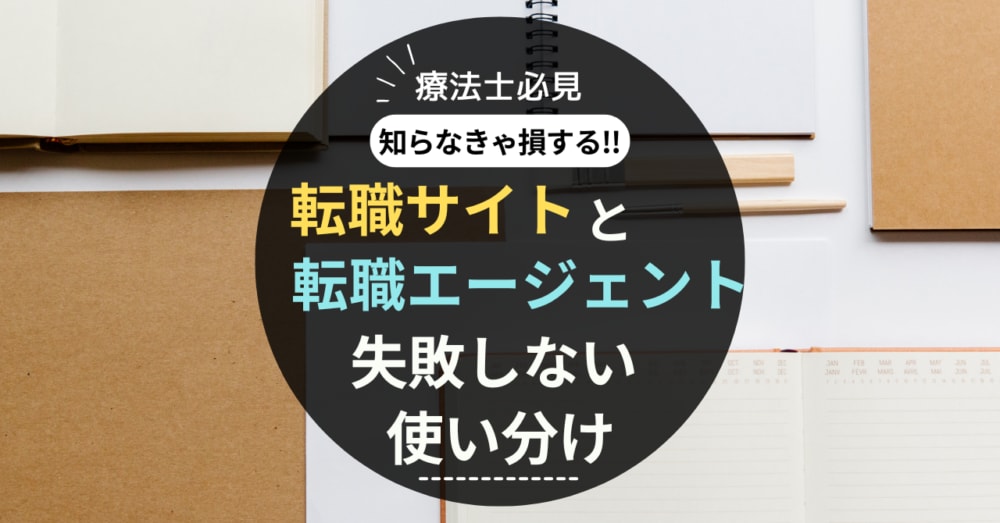








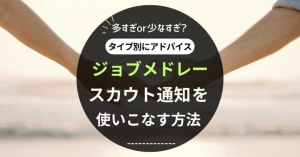


コメント