 こひつじさん
こひつじさん先輩から厳しく指導された💦
これってハラスメントじゃないの!?
リハビリ職として働く中で、このようなお悩みを持つ療法士さんは多いと思います。
そして逆に指導する側からすると
 療法士くん
療法士くんそんなつもりはないんだけどな…。どう指導したらいいか正直分からないよ
という声がチラホラ聞かれます。
このようなすれ違いが生むのが、「指導トラブル」です。
 おだかすみ
おだかすみ私の職場でも、この手のトラブルはとても多いんだ
トラブル解決に必要なのは、正しい知識とお互いの理解です。
この記事では、実際の事例を交えながら【適切な指導のポイント】と【指導を受ける側の心構え】を解説しています。
リハビリの現場で働く以上、指導する・される立場から逃れることは難しいもの。
この記事を読んで、私と一緒に “指導する側もされる側もハッピーな未来” を目指しましょう!!

- 病院、老健、特養で働くリハビリ職員30名のリハ科長
- 転職活動を行った結果、今の職場を選択
- 採用担当として10名以上を採用
- 40代50代の採用経験多数
第1章. 適切な指導とは – ハラスメント・不適切な指導との違い –

職場において、指導とハラスメントの境界線が曖昧になることは少なくありません。
特にリハビリの仕事は患者さんを相手にするものなので、先輩から後輩に指導する機会は必然的に多くなります。
ここで問題になるのは、適切な指導が行われているかという点。
「厳しい指導も成長のためには必要」と考える指導者も多いですが、受ける側にとっては精神的な負担となり、場合によっては職場環境の悪化につながることもあります。
ここでは、ハラスメントの定義や不適切な指導との違いについて解説し、適切な指導とは何かを明確にしていきます。
ハラスメントの定義
ハラスメントとは、職場において行われる精神的・肉体的な苦痛を伴う行為や、不当な扱いを指します。主な種類として以下のようなものがあります。
パワハラとは
パワハラ(パワーハラスメント)は、職場における優位性を乱用し、業務の適正範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為です。
厚生労働省の定義によると、パワハラは以下の3つの要素をすべて満たす必要があります。
- 優越的な関係に基づいて行われること
- 業務の適正な範囲を超えて行われること
- 身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること
モラハラとは
モラハラ(モラルハラスメント)は、倫理や道徳に反したいじめや嫌がらせを指します。主な特徴は以下の通りです。
- 範囲:職場だけでなく、家庭や友人関係など、様々な人間関係で発生する可能性がある。
- 定義:働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせる行為。
- 手段:言葉、態度、身振り、文書など様々な形で行われる。
- 影響:被害者が職場を辞めざるを得ない状況に追い込まれたり、職場の雰囲気を悪化させる。
- 特徴:直接的な暴力ではなく、精神的な暴力で相手を追い詰める。
セクハラとは
セクハラ(セクシャルハラスメント)は、職場における性的な言動や行為を指します。主な特徴は以下の通りです。
- 定義:他者を不快にさせる職場での性的な内容の発言や行為。
- 法的根拠:男女雇用機会均等法で定義され、防止が事業主の義務とされている。
- 範囲:職場で行われる労働者の意に反する性的な言動はすべてセクハラに該当する可能性がある。
- 例:髪や肩を無断で触る、愛人になるよう迫るなどの行為。
- 責任:加害者の意図に関わらず、被害者が不快に感じれば成立する可能性がある。
特にリハビリ職の職場では、パワハラやモラハラが問題になりやすい傾向があります。
時には厳しい指導が求められる場面もあるため、指導とハラスメントの区別を正しく理解することが重要です。
不適切な指導とは?
不適切な指導は、ハラスメントまではいかないが適切な指導でもない、という中間に位置します。
具体的には、指導する側の感情が前面に出てしまい、指導本来の目的が損なわれるような以下の行為が挙げられます。
感情的な指導:
・「なんでこんなこともできないんだ!」と怒鳴る
・人前で執拗に叱責し、必要以上に恥をかかせる
目的がズレている指導:
・「昔はこうやって覚えたから」と経験則だけで指導する
・具体的な改善策を示さず、「もっと勉強して」と根性論で終わらせる
このような指導は、受ける側にストレスを与えるだけでなく、成長の妨げにもなります。
では、適切な指導とはどのようなものでしょうか?
適切な指導とは
適切な指導とは、相手の成長を促すために行われる建設的なアプローチです。
不適切な指導との違いを明確にするため、以下のようなポイントを意識することが大切です。
| 不適切な指導 | 適切な指導 |
|---|---|
| 感情的に怒鳴る | 冷静に具体的な改善点を伝える |
| 罰を与えることが目的になっている | 失敗から学ぶ機会を与える |
| 指導者の過去の経験だけを押し付ける | 個々の状況に応じた指導をする |
| 人前で叱責する | プライベートな場で指導する |
適切な指導は、「指導される側が納得し、次に活かせるかどうか」がポイントになります。
上司や先輩の指導を行う際には、その内容が相手の成長につながるかどうかを判断基準とするとよいでしょう。
 療法士くん
療法士くん頭では分かるけど、実際どうすればいいの?
自分はそんなに間違ったことしてないつもりなんだけど…
指導のポイントを詳しく解説する前に、次章では、実際の現場で起こった指導トラブルをご紹介します。
何気なく行っていたことが相手にとってはハラスメントだった、という事態を意外と身近なものですよ。
第2章. 実際の現場で起こった「指導トラブル」

ここでは実際にあったケースをもとに、両者の言い分、そこから学べるポイントを見ていきましょう。
ケース1: 他者の前で指導する
 こひつじさん
こひつじさん患者さんの前で指導されるのがとてもつらかったです。患者さんにも聞こえてしまい、自分ができない人だと思われた気がします……。
 療法士くん
療法士くん患者さんが危ない場面で、すぐに改善してほしいからその場で指摘しました。そういう場合は仕方ないと思います。
 おだかすみ
おだかすみ今回のケースについては【適切な指導】と判断しましたが、急を要しない指導は1対1で行うことが基本です。
ここから学べるポイント
- 指導はできるだけ個別の場面で行う。
- 患者や他のスタッフの前で指摘すると、指導される側の自尊心を傷つける可能性がある。
- 安全のためにその場での指導が必要となった場合には、その意図を本人に伝える。
ケース2: 自分の経験則を押し付ける
 こひつじさん
こひつじさん離床訓練の時に、あれもこれもと細かいところまで言われて苦痛。そんな完璧にできる人なんているの?と感じました。
 療法士くん
療法士くん自分が今までやってきてうまくいった方法を伝えているだけですよ?
 おだかすみ
おだかすみ相手のレベル感に合わせて、順番に指導することが大切!!
ここから学べるポイント
- 自身の経験則だけでなく、エビデンスや施設のルールを基に説明する。
- 「なぜこの方法が必要なのか」を論理的に伝える。
- 相手の経験や理解度に合わせ、段階的に指導を行う。
ケース3: 具体的なフィードバックがない
 こひつじさん
こひつじさん『記録が不十分』と言われただけで、どう改善すればいいのか教えてもらえませんでした。
 療法士くん
療法士くん経験がある人なら、自分で気づいて改善してくれると思いました。他の人の記録を参考にするとか、やりようはあるよね?
 おだかすみ
おだかすみ分からないことは質問してほしいし、指導する側もやってほしいことは伝えるべき。コミュニケーション不足が原因のケースだね。
ここから学べるポイント
- 指摘する際は「何が不足しているのか」「どう改善すべきか」具体的に伝える。
- 「察してほしい」という姿勢ではなく、明確なフィードバックを心がける。
- 指導する側とされる側との意見交換の時間を持つ。
ケース4: 「自分で考えて」とやるべきことを教えてくれない
 こひつじさん
こひつじさんリハビリを引き継ぐ時に、すごく簡単な情報提供だけで終わりました。なのに後になって『私はこうしてたよ』とダメ出しされて。理不尽です!!
 療法士さん
療法士さんある程度は自分で考えてほしかったし、積極的に情報を取りに来る姿勢も必要だと思いました。
 おだかすみ
おだかすみ業務の遂行や患者さんのことを第一に考えていたら、お互いもっとコミュニケーションが取れたんじゃないかな?
ここから学べるポイント
- 「自分で考える力をつけさせる」ことは大切だが、適切なヒントを与えることも必要
- 必要な情報を小出しにするのではなく、全体像を伝えた上で考えさせる。
- 情報伝達の不足が業務の遅れや患者さんの不利益につながることを意識する
ケース5: 自分のいないところで悪口を言われた
 こひつじさん
こひつじさんこひつじの仕事ができないって周りのスタッフに言っていたのを聞きました。これは絶対ハラスメントです!
 療法士さん
療法士さんちょっと同僚に愚痴をこぼしていただけです。よくあることですよね?
 おだかすみ
おだかすみ働く人間の人格や尊厳を傷つけているのであれば、これは【モラルハラスメント】にあたる可能性あるよ!
ここから学べるポイント
- 無責任に職員の悪い話を広めない
- 職員の人格や尊厳を尊重する
- 指導方針を他者に相談するのであれば、場所と相手を選ぶ
これらの事例からも分かるように、リハビリテーションの現場では指導方法をめぐる意見の食い違いが発生しやすいです。
行動次第では【不適切な指導】や【ハラスメント】に含まれてしまう場合があるため、特に指導者側は「これは適切な指導です」と胸を張って言えるようにしておく必要があります。
次章では、指導者が適切な指導を行うためのポイントを解説します。
第3章. 【指導者向け】適切な指導を行うためのポイント

適切な指導を行うためには、相手の受け取り方や職場の雰囲気を考慮しながら伝えることが重要です。指導を円滑に進めるためのポイントはこちら。
- 目的を明確に伝える
- 具体的なフィードバックをする
- 相手の立場を尊重する
- 感情的にならず冷静に対応する
- 成長をサポートする意識を持つ
順番に見ていきましょう。
1. 目的を明確にする
指導の目的は、単なるミスの指摘ではなく、スタッフの成長を促し、より良い医療サービスを提供することです。
目的が明確でない指導は、単なる押し付けや批判と受け取られる可能性があります。
「このやり方はあんまり良くないよ。」
「この技術を習得すると、患者さんの負担が減るよ。一緒に練習しよう。」
目的を明確に伝えることで、指導される側も納得感を持って学ぶことができます。
2. フィードバックは具体的に
指導の際には、「ダメ」「違う」といった曖昧な言葉ではなく、具体的な改善策を提示することが重要です。指導される側が何をどう直せばよいのか分からなければ、指導の意味を成しません。
「記録が不十分だから、もっと詳しく書いて。」
「この部分に患者さんの経過を詳しく書くと、他のスタッフも判断しやすくなるよ。」
改善の方向性を明確にすることで、相手が実践しやすくなります。
3. 相手の立場を考える
指導者の経験が豊富であるほど、「自分が若手のころはこうだった」と考えがちですが、状況や個々のレベルが異なることを認識する必要があります。
自分の成功体験だけを押し付けるのではなく、相手の考えを尊重しながら指導を行いましょう。
「私の時はこの方法でうまくいったよ。あなたもやってみて。」
「この方法は私が経験した中で効果的だったけど、あなたのやり方でもうまくいくかもしれないね。一緒に考えてみよう。」
相手を尊重しながら指導を行うことで、納得感のある指導になります。
4. 感情で怒らない
感情的に怒ってしまうと、指導される側は委縮し、本来の目的である「成長の促進」が妨げられてしまいます。冷静にフィードバックを行うことで、信頼関係の構築につながります。
(怒鳴る)「何度言ったらわかるの!」
「前回も同じミスがあったね。原因を一緒に考えて、解決策を見つけよう。」
冷静に伝えることで、相手も前向きに改善へ取り組めます。
5. 相手の成長をサポートする意識を持つ
指導者は、単に業務を教える立場ではなく、相手の成長を支援する役割を担っています。そのためには、短期的な結果だけでなく、長期的な視点で相手のスキルアップを考えることが重要です。
「とりあえずこの仕事だけ、ミスなくやってくれればいいから。」
「新しいことに挑戦してみると、自分の強みが増えるよ。興味があればサポートするね。」
単なる業務の遂行ではなく、相手の成長を支える姿勢が指導者には求められます。
指導がハラスメントとならないように意識しながら、相手の成長を促す「適切な指導」を心がけていきましょう。
しかしこんな話をすると、
 療法士くん
療法士くん指導って指導者だけが気を使えばいいこと?
 療法士さん
療法士さん指導をしても無視して聞いてくれない人もいるんだけど…
と感じる指導者の方も多いと思います。
もちろん、指導される側の姿勢も大切です。指導される側はただ受け身でいるのではなく、指導を前向きに捉え、適切に対応することが求められます。
次章では、指導を受ける際の心構えについて解説します。
第4章.【指導される側向け】指導を受ける際の心構えと対処法

指導を受ける側の姿勢次第で、成長の機会にすることも、ただのストレスで終わらせてしまうこともあります。本章では、指導を前向きに捉え、スキルアップにつなげるためのポイントを解説します。
1. 指導を「成長のチャンス」と捉える
指導は、単なる注意や批判ではなく、成長の機会です。特に経験豊富な指導者からのアドバイスは、実践的な知識を学ぶチャンスと捉えましょう。
「また怒られた…自分はダメなんだ。」
「指導を受けたということは、期待されている証拠だ。」
成長のためのヒントと考え、前向きに受け止めることが大切です。
2. まずは冷静に受け止める
指導の内容が厳しく感じることもありますが、感情的に反応せず、一度冷静になりましょう。
指導の背景には、職場全体のレベルアップや患者さんのための意図があることを意識すると、受け入れやすくなります。
「この人の指導は受けたなくないから無視しよう」
「指摘の意図を理解しよう。どう改善すればいいか考えよう。」
感情的にならず、指導の本質を見極めることが重要です。
3. 分からないことは素直に質問する
分からないことや納得できないことがあれば、素直に質問しましょう。ただし、質問の仕方によっては「言い訳」と受け取られることがあるため、伝え方には注意が必要です。
「でも、それは○○さんもやってましたよね?」
「具体的にどのように改善すればいいでしょうか?」
建設的な質問をすることで、学びを深めることができます。
4. 自分なりに改善策を考える
指導を受けた後、そのまま終わりにせず、「次にどう活かせるか」を考えましょう。実際に改善しようとする姿勢を見せることで、指導者との関係も良好になります。
(指導後何もしない)「怒られたけど、そのうちできるようになるだろう。」
「指摘された点を改善するために、次回はこうしよう。」
指導を受けっぱなしにせず、自分なりの工夫を加えることが成長につながります。
5. 指導が行き過ぎていると感じたら
指導が度を越している場合は、適切に対応することも必要です。ハラスメントに該当する可能性がある場合は、信頼できる上司や第三者に相談しましょう。
「耐えるしかない…。」
「内容が指導の範囲を超えていると感じるので、相談してみよう。」
精神的な負担を抱えすぎず、適切な対処をすることも大切です。
まとめです。
指導を受ける際には、
- 成長の機会と捉える
- 冷静に受け止める
- 分からないことは建設的に質問する
- 自分なりに改善策を考える
- 行き過ぎた指導には適切に対処する
ことが重要です。指導を前向きに受け止めることで、自身のスキルアップにつなげていきましょう。
 こひつじさん
こひつじさんそれでも理不尽な指導をされたら、どうしたらいいの?
最終章では、やれることはやったけど事態が改善しなかった場合の対処法を解説します。
第5章. それでも改善しない場合の対処法 3 選

指導される側が前向きに対応しようと努力しても、状況が改善しないこともあります。そのような場合、次の対策を検討しましょう。
1. 職場の相談窓口や上司に報告する
もし指導が度を越していると感じたら、職場の相談窓口や信頼できる上司に相談することがまず第一手です。報告する際のポイントは以下の通り。
- 記録を残す(指導の内容や日時をメモする)
- 冷静に事実を伝える
- 「こう改善してほしい」という具体的な要望を伝える
ただし、相談する相手を間違えると逆効果になる場合もあるため、職場の環境を見極めて慎重に行いましょう。
2. 社外の相談機関を利用する
社内で解決が難しい場合は、社外の相談機関を活用するのも一つの手です。以下のような機関が相談に応じてくれます。
労働基準監督署(総合労働相談コーナー)
労働問題全般に関する相談窓口です。厚生労働省が各都道府県労働局と労働基準監督署に設置しています。主に賃金未払い、残業代未払い、休憩時間の未取得、有給休暇の取得拒否などが相談の対象となります。
連絡先:
- 東京労働局 総合労働相談コーナー: 03-3512-1608
- 受付時間: 9:00~17:00(平日)
こころの耳(厚生労働省)
働く人のメンタルヘルスに関する相談窓口です。職場での悩みやストレスを一人で抱え込まずに、専門家のサポートを受けながら問題解決に向けて取り組むことができます。
また、自分のメンタルヘルスの状態を客観的に把握し、適切なケアを行うきっかけにもなります。
連絡先:
- 電話相談: 0120-565-455 または 0120-926-097
- SNS相談、メール相談も利用可能
ハラスメント悩み相談室
職場でのハラスメントに関する相談窓口です。厚生労働省が運営しています。状況に応じた適切な対応策や解決方法についてのアドバイスが得られ、関連する法律や制度、他の相談窓口などの情報が提供される場合もあります。
連絡先:
- 電話: 0120-714-864
- 受付時間: 平日 17:00~22:00、土・日 10:00~17:00
- メール、LINEは24時間受付
法テラス(日本司法支援センター)
法的トラブルに関する情報提供や相談窓口です。解決に役立つ法制度や適切な相談窓口の情報を無料で提供しています。1回30分程度、同じ問題について3回までという制限がありますので、相談する際はポイントをまとめておきましょう。
連絡先:
- 法テラス・サポートダイヤル: 0570-078374
- 犯罪被害者支援ダイヤル: 0120-079714(平日9時~21時、土曜9時~17時)
これらの機関は、労働問題、メンタルヘルス、ハラスメント、法的トラブルなど、様々な問題に対応する相談窓口を提供しています。必要に応じて適切な窓口に相談することをお勧めします。
 おだかすみ
おだかすみ外部の専門家に相談することで、自分では気づかなかった解決策が見つかることもあるよ。
3. 指導トラブルが起こりにくい職場に転職する
問題が解決しない場合、最終手段として転職を考えるのも選択肢の一つです。
 こひつじさん
こひつじさんて、転職って、逃げじゃないの?
 おだかすみ
おだかすみ転職は逃げじゃない!!
と、私が言い切れる理由はこちらです
- 心身の健康を守ることが最優先だから
- 今の職場だけがすべてではないから
- 相手が変わるのを待つよりも、自分の行動や環境を変えた方がはるかに確実だから
 こひつじさん
こひつじさんでもまた同じことになるんじゃないかと心配だよ〜
 おだかすみ
おだかすみ次の職場は指導トラブルが起こりにくい所を選びたいね
転職を決断する際は、次の職場が同じ問題を抱えていないか慎重にリサーチする必要があります。
- 転職エージェントに「指導環境」について質問する
- 職場見学で「指導の雰囲気」を観察する
転職エージェントに「指導環境」について質問する
転職エージェントには退職を考える人の生の声が集まります。そのため、活用することで職場のリアルな状況(指導体制、人間関係、労働環境など)を事前に知ることが可能です。
ただしエージェントも積極的に悪い話を広めようとはしないため、こちらから質問をすることが必要となります。
質問の仕方
- 「入職職員の教育体制はどのようになっていますか?」
- 「指導の際にトラブルが起きたことはありますか?」
- 「指導者の特徴や、人間関係での離職者の有無を知りたいです」
ポイント: 具体的な質問をすることで、エージェントも隠さず情報を教えてくれる
転職エージェントの選び方は、こちらの記事を参考にしてくださいね。
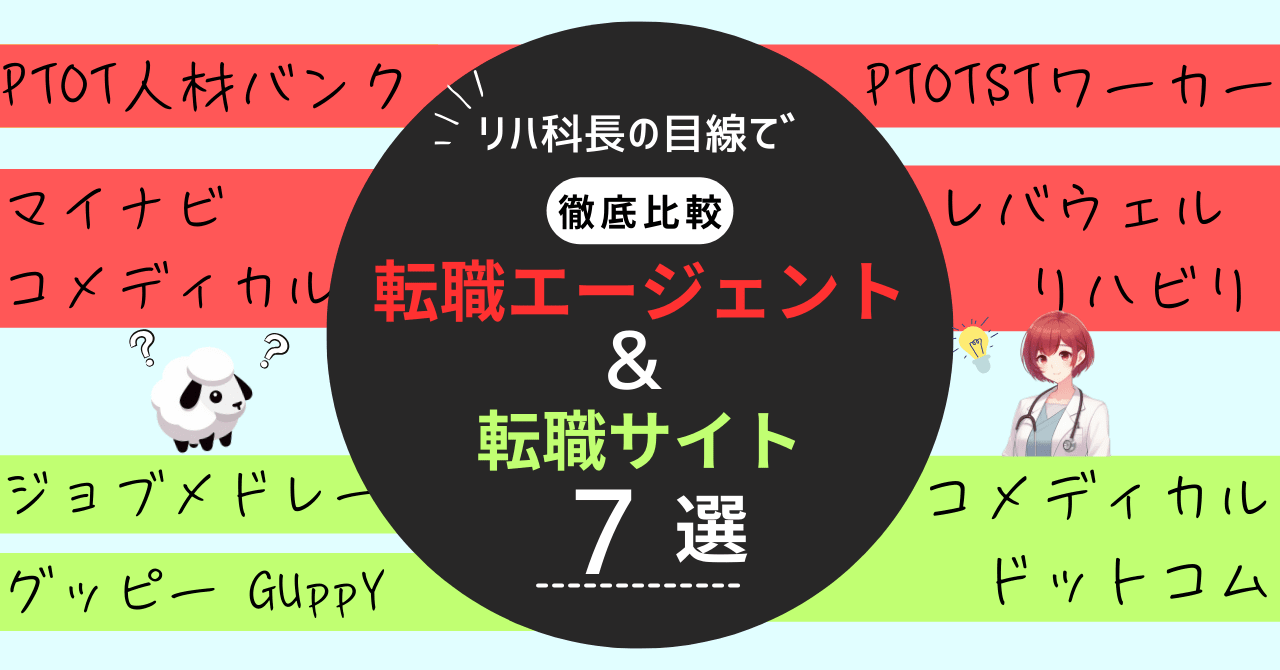
職場見学で「指導の雰囲気」を観察する
実際に現場を見ると リアルな人間関係や雰囲気 がわかります。
チェックポイント
- 指導者(主任・リーダー)の部下との接し方
- 圧力的・命令口調ではないか?
- 部下が萎縮せず、質問しやすい雰囲気か?
- 一般スタッフの表情 を見る
- 自然体なら良い職場、緊張や焦りが見えるなら要注意
- スタッフ同士の会話 に笑顔や雑談があるか?
- 余裕がある職場は指導も適切なことが多い
ポイント: 上司・ベテラン層の態度が厳しすぎないかを重点的に観察
 おだかすみ
おだかすみ職場見学では他にもいろいろなことを知ることができるよ!
▼こちらの記事も参考にしてね▼

まとめ
指導に関するトラブルは、指導する側・される側それぞれに言い分があり、どちらか一方が悪いとは言い切れません。
指導者としては「適切に教えているつもり」でも、受け手にとっては厳しく感じることもありますし、その逆も然りです。
大切なのは、お互いが より良い指導環境をつくるために何ができるか を考え、行動すること。
指導する側は、相手に合わせた伝え方を意識し、威圧的にならないよう配慮する。指導される側も、分からないことを遠慮せず質問し、素直な気持ちで学ぶ姿勢を持つ。
そして、もし 今の職場でどうしても指導が合わない、ストレスが大きい と感じたら、環境を変えることも一つの選択肢です。転職する際には、次の職場で同じ問題を繰り返さないよう、事前のリサーチや見極めをしっかり行いましょう。
 おだかすみ
おだかすみお互いにとっての「働きやすい職場」を模索していこう!!
▼ こんな記事も書いてます▼

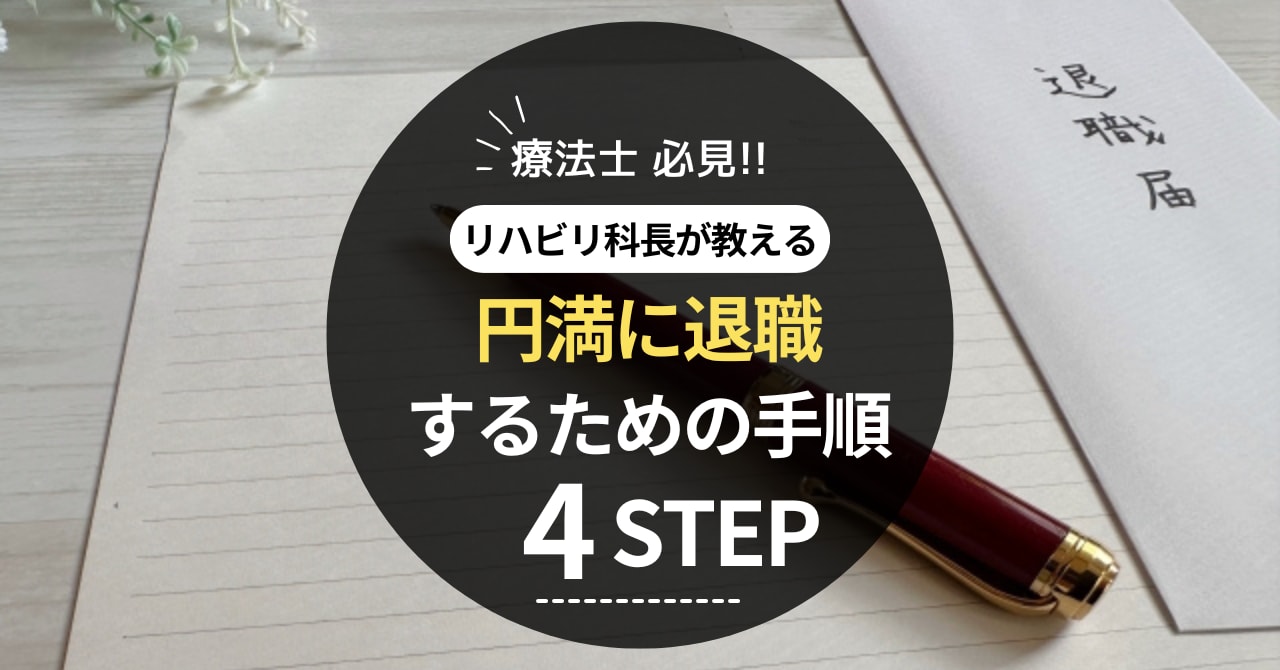
ここまでお読みいただきありがとうございました!!
またお会いしましょう!!







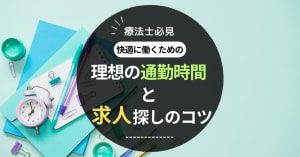
コメント