「昇進すれば年収は上がる。だけど、現場から離れるのはイヤだな…」
「このままプレーヤーとして働き続けていいのか、不安になってきた…」
そんなモヤモヤを感じている療法士の方も多いのではないでしょうか。
40代以降になると、昇進やキャリアアップは現実的で切実なテーマになります。
昇進したいと思ってもなかなかチャンスが回ってこなかったり、
逆に「本当は現場が好きなのに」と思いながら昇進させられてしまったり。
それぞれの立場での悩みや葛藤があるのが、今の療法士の現場です。
この記事では、私自身の経験をもとに
- 昇進して得られたこと
- 昇進してしんどかったこと
- どんな人が管理職に向いているのか
- 昇進しない道を選ぶときの考え方
などを、リアルに・包み隠さずお伝えしていきます。
「この先、自分はどう働いていきたいのか?」
その答えを探すきっかけになれば幸いです。

- 病院、老健、特養を統括するリハ科長
- 転職活動を行った結果、今の職場を選択
- 採用担当として10名以上を採用
- 40代50代の採用経験多数
1. 昇進して得られたこと

昇進したことで得られたものは、想像以上に大きなものでした。
もちろん責任や苦労もありますが、「昇進してよかった」と感じられる瞬間は、確かにあります。
現場を動かせる「決定権」
昇進して最も大きく感じたのは、「自分の判断で現場を改善できるようになったこと」です。
以前は、現場の声を上げても上の判断で「変えられません」と却下されてしまうことも多く、「なんでこんな非効率なままなの?」と感じる場面がたくさんありました。
ですが今は、現場の声を聞きながら自分で決めて変化を起こせます。
これは、プレーヤー時代には得られなかった大きなやりがいでした。
体験談はこちら
私がまず取り組んだのは、病院と関連施設間の情報提供書の簡略化でした。
ずっと紙での細かい書式を使ったやり取りが続いていて、現場は大きな負担を感じていました。科長になってからは自分の判断で書式を見直し、ロック付きのデータをメールで送る運用へ変更。
また、家族宛て書類の郵送もすべて科長が確認するルールでしたが、チェック項目を共有し、現場の職員同士でダブルチェックすればOKという形に切り替えました。
結果、業務負担が減り、現場の職員がより患者さんと向き合える時間を確保できるように
未来を描き、仕組みを整える楽しさ
私はもともと、「どうすればもっと良くなるか」を考えるのが好きなタイプです。
昇進してからは、未来を想像して、リハビリ科をどう育てるかを考える時間が増えたことで、
新たなやりがいを感じるようになりました。
💡 今はこんなことを想像するのが楽しい毎日
- リハ科が法人の利益にどう貢献できるか?
- 職員がより働きやすい仕組みはどう作るか?
- 数字(売上や稼働)をどうやって伸ばしていくか?
 おだかすみ
おだかすみ未来のビジョンを描いて、仕組みをつくっていけるのは楽しい!
“目の前の1人”ではなく、“全体にとっていいこと”を考えられる立場にやりがいを感じています。
年収アップ
昇進によって、役職手当がつくなど収入面のメリットももちろんあります。
これによって、
- 毎月の貯蓄・投資にまわせるお金が増えた
- 将来への不安が減った
- 家族の希望も聞きやすくなった
など、リアルに「生活が安定する」という効果を感じています。
若い頃は「お金よりやりがい!」と思っていましたが、40代、50代になると家族のこと、老後のことなど、“守るべきもの”が増えてくるもの。
 おだかすみ
おだかすみ昇進による年収アップは、心に余裕を生んでくれたよ
まとめ:昇進のメリットは“やりがい”と“選択肢”が増えること
- 自分の判断で現場を動かせること
- 未来を想像して働けること
- 年収が上がって生活に安心が生まれること
昇進は大変なこともありますが、「やれることが増える=自分の可能性が広がる」という前向きな側面もたくさんあります。
以上が、私が管理職になって「昇進してよかった」と感じているポイントです。
2. 昇進してつらくなったこと

昇進して得られるものがある一方で、「思っていたより大変…」と感じることもありました。
ここでは、昇進して初めて気づいた“リアルなしんどさ”を3つご紹介します。
患者さんと向き合う時間が激減
プレーヤー時代は、患者さんと直接関わる時間が仕事の中心でした。
でも昇進後は、職員対応・会議・調整・資料作成などの比重がぐっと増加します。
📌 「患者さんの変化に関われる」という手応えが薄れてしまう
「人の役に立ちたくてこの仕事を選んだのに…」
そんなジレンマを感じることも、決して少なくありません。
 おだかすみ
おだかすみ私も元々は、患者さんとじっくり向き合う時間が好きでした
おだかすみの実体験はこちら
科長に昇進後、現場に出る時間が減り、気づけば1日PCの前で資料を作ったり、人間関係の調整をしたりする日々に。
「これ、私がやりたかった仕事だっけ?」
そんな思いが頭をよぎったこともあります。
患者さんの反応に直接ふれられる“あの感覚”が恋しくなって、今は少しでも現場に出る時間をつくるよう、意識するようになりました
「やっぱりこの仕事が好きだな」と思える時間が、自分のエネルギーになっています。
職員の不満や葛藤を受け止める立場に
昇進すると、立場が変わります。
今までは職員の一人として「同じ目線」で話せていたのに、管理職になった途端、「意見」ではなく「指示」になるんですよね。
人間関係のバランスが微妙に変わるのを感じるのは、多くの人が通る道かもしれません。
 おだかすみ
おだかすみ周りの職員との関係性が変化し、孤独を感じることもありました
私の体験談
昇進したばかりの頃は、
「急に距離を取られてる?」
「言葉ひとつで空気が変わる…」
と感じることもありました。
ただ私は幸運にも、長く一緒にやってきた仲間たちが“副主任”や“主任”として支えてくれたことで、孤独感はだいぶ軽減されました。
今でも「チームでやっている感覚」があるからこそ、管理職として続けられていると思います。
体を動かす時間が減り、健康面に変化も
デスクワーク中心になることで、体を動かす機会が激減します。
もともとアクティブに動く仕事をしていた方ほど、この変化に戸惑うかもしれません。
肩こり・目の疲れ・運動不足…
まさか自分がこうなるとは、という変化に直面することもあります。
 おだかすみ
おだかすみ前は肩こりなんて無縁だと思っていましたが、今は違います
私の体験談
現場にいた頃は自然と体を動かしていたので、運動不足なんて無縁でした。
でも昇進してからは、1日中座りっぱなしのことも多く…。
気づけば肩こりと眼精疲労がひどく、体重もじわじわ増加。
これは本当に盲点でした。
今は意識的にストレッチや軽い運動を取り入れるようにしていますが、「体を動かす仕事って、実は健康にも良かったんだな」としみじみ思います。
まとめ:昇進には“ギャップ”がある。けれどそれも学び
こうしたギャップに悩みながらも、私は「昇進してよかった」と今は感じています。
でもこれは、自分の性格や価値観に合っていたからこそかもしれません。
それでは次に、どんな人が管理職に向いているのか?逆に向かないのはどんなタイプか?
その違いを見ていきましょう。
3. 管理職に向いている人・向かない人

昇進は、誰にとってもプラスになるわけではありません。
向き・不向きを見極めずに昇進すると、本人にとっても組織にとっても残念な結果になってしまうこともあります。
ここでは、「管理職に向いている人・向かない人」の特徴を整理してみます。
管理職に向いている人の特徴
全体を見通す力がある
管理職になると、「自分の仕事」だけでなく、部署全体や法人全体の動きを把握する必要があります。
視野が狭いままだと、判断が独りよがりになったり、チームを正しく導くことができません。
📌 目の前のことだけでなく、全体の最適解を探れる人は、管理職として力を発揮しやすいです。
 おだかすみ
おだかすみ私も昇進後、“現場の効率”と“他部署との連携”の両方を考える場面が増えたよ
広い視野で考える力は、現場感覚とはまた違うスキルが必要になると感じています。
職場への貢献意識が強い
「職場全体のために、より良くしたい」という気持ちを持って行動できる人は、自然と信頼され、昇進のチャンスが巡ってきやすいです。
これは感情や性格だけでなく、発言のしかたや行動パターンにも表れます。
“自分の業務”だけを守るのではなく、“職場の仕組みごとよくしたい”という視点を持つこと。
それを意識できる人は、ぜひ管理職の道に進むことも考えてみてください。
指導・調整に前向きに取り組める
管理職は、単に「上に立つ人」ではなく、チームを支える裏方的存在でもあります。
- 職員の育成
- 他部署との業務調整
- トラブル時の間に入る役割
これらを「面倒」ではなく「やりがい」と感じられる人は、マネジメント職に向いています。
 おだかすみ
おだかすみ私自身、自分のお客様が「患者さん」から「職員」にシフトしたように感じているよ
裏方にまわって支えることになるので、”このチーム嫌いだな”と感じている場合には、大きな苦痛を感じることになるでしょう。
管理職に向かない人の特徴
現場の仕事が何より好き
リハビリ職の中には、患者さんと直接関わること自体に強いモチベーションを持っている方も多くいます。
その場合、現場を離れることが苦痛になりやすく、昇進はかえってストレスになることも。
📌 「人の役に立ちたい」という気持ちは大切ですが、それが“直接的な支援”に限定されていると管理職業務は苦しくなりやすいです。
 おだかすみ
おだかすみ私の場合は、現場に出る時間が1/3〜1/4くらいになったよ
管理業務に興味がない
- 会議
- 人事評価
- 数値管理
- 書類作成
…など、現場とは全く違うタイプの業務が管理職には多くあります。
📌 こうした業務に対して「苦手意識が強すぎる」「興味を持てない」という人は、昇進後に燃え尽きてしまう可能性があります。
 おだかすみ
おだかすみ「苦手」は克服できる可能性があるけど、「完全に興味がない場合」は要注意!
感情的になりやすい
管理職は、対人ストレスとの付き合い方も大きなカギになります。
職員との関係、上司との関係、外部対応など、感情のコントロールが求められる場面は多いです。
📌 「なぜそんなことを言うの?」と思ったときに、相手の背景や立場を想像して対応できるかどうかが、管理職として信頼を得られるかの分かれ道になります。
 おだかすみ
おだかすみ感情と事実を分けて考え、クールに対応することが大切!
まとめ:大切なのは「昇進するべきか」ではなく「昇進が自分に合っているか」
ここまで読んでみて、
「うん、私は管理職向いてるかも」と感じた方もいれば、
「ちょっと興味はあるけど、自信がないな…」という方もいるかもしれません。
どちらにしても、昇進を目指すためには“きっかけ”と“動き方”が必要です。
次の章では、“昇進に近づくための行動パターン”をこっそりお話しします。
4. 昇進を目指すなら、戦略が必要

「がんばっていれば、いつか誰かが見てくれる」
そう思いたいのは山々ですが、昇進には“戦略的な動き方”が必要です。
ここでは、私自身の経験をもとに、昇進を目指す人にぜひ知っておいてほしい3つのポイントをお伝えします。
職場全体への「貢献意識」を持つ
管理職は、「職場のためにどう動けるか」が問われるポジションです。
だからこそ、自分の行動や発言が“チーム全体にどう影響するか”を考えられる人が昇進候補に近づいていきます。
📌 職場において、「自分の仕事だけやればOK」というスタンスの人は珍しくありません。
- 自分の業務を定時内にサクッと終わらせて帰る
- 与えられた範囲の仕事だけをきっちりこなす
これはこれで“仕事が早くて優秀”なプレーヤーなのですが、それを周囲に波及させる力がある人は、ほんの一握りです。
 おだかすみ
おだかすみ“みんなが早く帰れる仕組み”を考えられる人を目指してみよう
管理職は、「職場のためにどう動けるか」が問われるポジションです。
だからこそ、日頃から自分の発言や行動が“全体にどう影響するか”を意識している人は、昇進候補として見られやすくなります。
「提案する力」をつける
現場の課題に気づける力は大切ですが、それ以上に評価されるのは、「どうしたら良くなるか」を提案できる力です。
日々のちょっとした不便さや疑問を、「こうしたらどうですか?」と前向きに伝えることで、「この人は“よくしたい気持ち”を持っている」と周囲に伝わります。
注意したいのは、“不平不満”だけで終わらせないこと。
たとえば──
✖「あの制度、使いづらいですよね」
と言いっぱなしで終わるのではなく、
◎「こういうふうに見直すと、現場がもっと回りやすくなると思います」
と具体的な提案を一緒に伝えることが大切。
日常のちょっとした「気づき」や「不便さ」を、「こうしたらどうだろう?」と自分の言葉で伝える力を持っている人はなかなかいないため、重宝されやすいです。
 おだかすみ
おだかすみ完璧な提案じゃなくてもOK!
「こういう工夫どうですか?」の一言が、あなたの存在感を変えてくれます。
人を悪く言わない
昇進を狙う場面で、他人を下げて自分を上げようとする言動を取る人がいます。
ですが実際には、そうした発言は評価されるどころか、信頼を落とす要因になりやすいです。
📌 「○○さんが足を引っ張ってる」「あの人がいなければもっと上手くいく」
──そうした言い方は、組織全体にとってもマイナスに働きます。
どうしても困った人・状況があるなら、
「何が業務の支障になっていて、どう改善すると全体にプラスになるか」までを提案できるのが理想です。
 おだかすみ
おだかすみ人が陰口を言っている場面からは、そっと離れそう
まとめ:昇進には適切な“がんばり方”がある
📌 昇進に必要なのは、がんばり続けることではなく、“正しい方向に動くこと”です。
次の章では、「自分は昇進したくなんてしたくない!」という方に向けて、昇進しない選択とその伝え方についてお話しします。
5. 昇進したくないあなたへ

昇進を目指す人がいれば、もちろん「昇進したくない」と感じる人もいます。
それは甘えでも逃げでもなく、自分の価値観や働き方を大切にする正当な選択肢です。
この章では、昇進を望まない人が抱えがちなモヤモヤと、そのうえでどう動けば「自分らしく働き続けられるか」についてお伝えします。
あいまいな態度が、いちばん疲れる
職場によっては、年齢や在籍年数だけで“そろそろ昇進を”と期待されることもあります。
でもそこであいまいな態度をとっていると──
- 「やる気がないのかな?」と思われてしまったり
- 逆に「受けてくれるんだ」と誤解されて話が進んでしまったり
📌 結果的に自分も周囲も疲れてしまうことになります。
 おだかすみ
おだかすみだからこそ、「昇進は望んでいません」と誠実に、はっきり伝えることが大切!
伝え方としては、“現場で力を発揮し続けたい”というポジティブな表現がおすすめです。
否定ではなく、希望として伝えると、職場との関係も良好に保つことができます。
「現場が好き」は立派な理由になる
管理職になれば、現場に出る時間はどうしても減ります。
人と向き合う時間が、“書類や会議、人間関係の調整”に変わっていくのは避けられません。
 おだかすみ
おだかすみ“現場で手を動かしている方が楽しい”という人は、それが自分の強みだと自信を持っていいです!
「患者さんの近くで働きたい」という想いは、十分に昇進を選ばない理由になります。
まとめ:「昇進しない」ことは逃げではなく、選択
📌 無理に上を目指さなくても、納得して働ける道はきっとあります。
とはいえ、現実には…
- 「昇進したくても、全然チャンスが回ってこない」職場
- 「昇進したくないのに、気づけばポストを任されそうになる」職場
どちらも存在します。
次章では、あなたの職場が“自分の進みたい道”にマッチしているかどうかを一緒にチェックしてみましょう。
6. 昇進しやすい職場・昇進しにくい職場

昇進を目指すにせよ、望まないにせよ、大切なのは、“今の職場が自分が進みたい道と合っているかどうか”を見極めることです。
この章では、私の経験から、昇進しやすい職場/しにくい職場の特徴をまとめました。
今の職場がどちらに当てはまるのか、ぜひ照らし合わせてみてください。
- 管理職の枠が空いている
- 競争相手が少ない
- 評価制度がはっきりしている
- 管理職の枠が埋まっている
- 競争相手が多い
- 評価制度が曖昧
▼ 詳しくはこちらの記事で解説しています ▼

今の職場は自分の進みたい道に合ってる?
昇進したい人にとっても、昇進したくない人にとっても、“自分がどこで働くか”はキャリア形成において非常に重要です。
今の職場は…
- 自分の頑張りが見えやすい環境ですか?
- 昇進の基準やルートが明確ですか?
- 昇進を希望しない場合でも、自分の意思を尊重してくれますか?
「なんか違うかも…」と思ったなら、職場を変えることを視野に入れるのもひとつの方法です。
「なんか違うかも…」と思ったら
「今の職場だと昇進できないかも」
「現場にいたいのに昇進させられるかも…」
そう感じたとき、職場を変えることを視野に入れてみましょう。
 こひつじさん
こひつじさんこの歳で転職なんて、遅すぎない?
 おだかすみ
おだかすみ療法士の場合、40代50代でも採用される人はたくさんいるよ!
 こひつじさん
こひつじさんでも…次の職場でも同じことになったらどうしよう
これは、多くの人が感じる不安です。
せっかく意を決して転職したのに、また「昇進できない」「無理に昇進させられる」なんてことになったら本末転倒ですよね。
求人票だけではわからない情報──
- 昇進の基準や評価制度
- 管理職の働き方や残業時間
- 組織の風土やポストの動きやすさ
こうした情報を知るには、実際に働いた人の話を聞くのが一番確実です。
 こひつじさん
こひつじさんそんな知り合いなんていないよ〜
そんな時に頼りにしたいのが、転職エージェントです。
転職エージェントには、数々の療法士の「転職前の不満」や「転職後のリアルな状況」といった生の声が集まっており、かなり現実に近い情報を把握しています。
自分の「やりたい働き方」も含めて、まずは相談してみよう
転職活動=すぐに辞める、という話ではありません。
「今の職場とどう向き合うべきか」「他にどんな働き方があるのか」
そんな不安や迷いも、一人で抱え込まずに、プロに相談してみるのが賢い選択です。
私のブログでは、療法士向けの転職支援に特化したエージェントとしてこちらの2社を推薦しています。
\ わたしも使ってよかった /
▲ 60秒で簡単登録、ずっと無料 ▲
\ 業界最多の求人にアクセス/
▲ 簡単登録、無料で相談 ▲
 おだかすみ
おだかすみもっとじっくり考えたい人は、こちらの記事も参考にしてね👇
まとめ:昇進する・しない、どちらも正解
昇進することにはメリットもあれば、覚悟も必要です。
一方で、昇進しない選択にも、自分の働き方を貫けるという価値があります。
このブログ記事を通してお伝えしたかったのは、「どちらを選ぶにしても、納得して選ぶことが大切」ということです。
- 現場で力を発揮し続けたいなら、それも立派なキャリア
- 上を目指したいなら、戦略と環境選びがカギ
- どちらにしても、「今の職場が自分に合っているか」を見直すことが第一歩
キャリアに迷ったら、一人で抱え込まず、信頼できる人に相談してみてください。
私が実際に使ってよかった転職エージェントもぜひご活用ください👇
\ 寄り添い力に定評あり /
▲ 60秒で登録、ずっと無料 ▲
 おだかすみ
おだかすみあなたの挑戦を、心から応援しています!
それでは良き療法士ライフを!
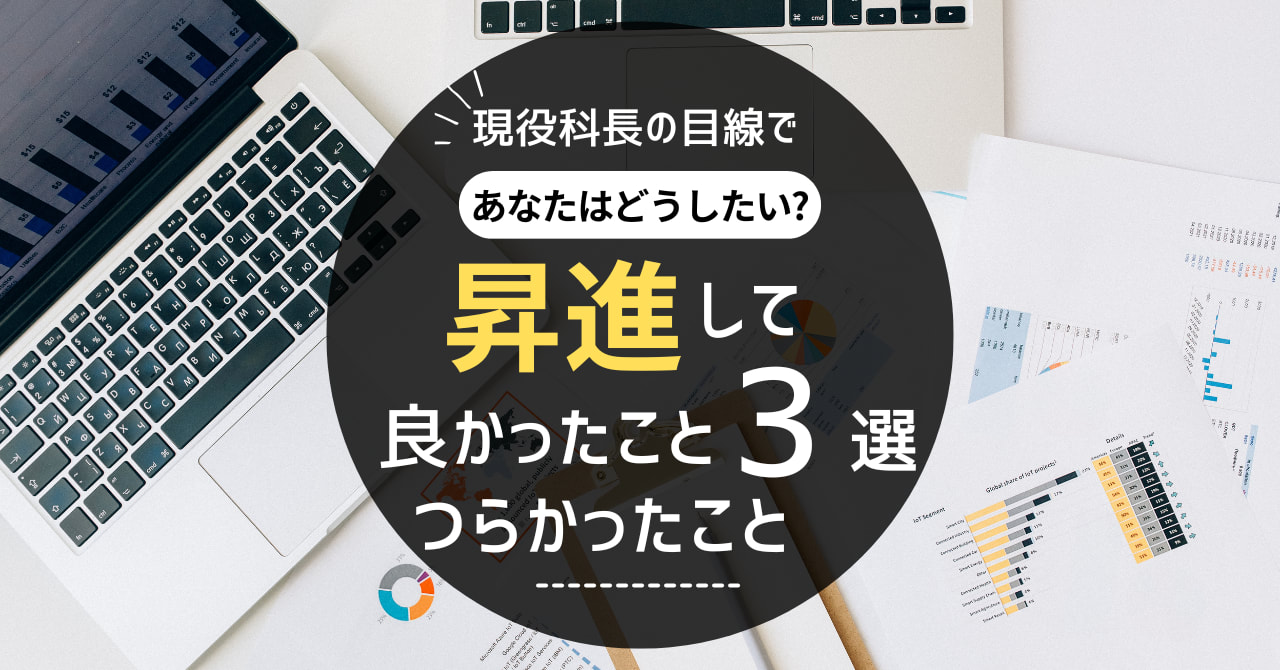






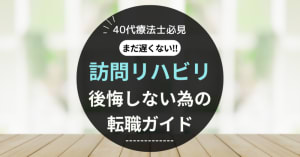


コメント